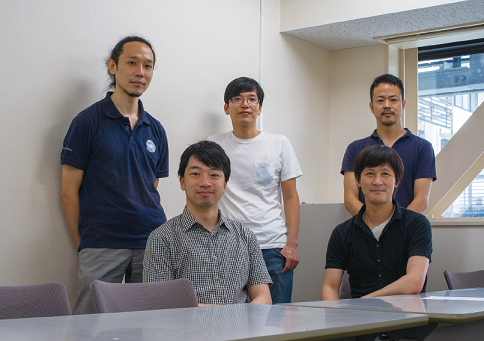シリーズ白眉対談17「COVID-19 対策最前線特集」(2020)
中国のウイルス研究
水本 感染症のデータ分析で驚いたのは、最近の中国がすごい。中国から出てくるデータ解析は圧倒される物量ですね。論文の質はある程度置いといて、量が圧倒的に多くて、日本とはスピード感も違いすぎる。
司会 基礎研究も中国の勢いがすごい。本当に、レベルも。
堀江 レベルがすごいよね。基礎も完全に。思い切りもすごいし、もちろんピンキリではあるんですけど。
司会 クオリティーの高い論文が、スピード感を持ってアメリカと中国ででている。
古瀬 そもそも、新型コロナがみつかった出発地点がすごくて、2019年12月初頭に、普段と違う肺炎が武漢で流行したとき「これはおかしいからウイルスのゲノムを調べよう」って、普通の町医者が思って調べてみたら見つかった。もし日本でこれが起こったら、半年くらい見つからなかった可能性もあると思うんですよね。その町医者が「何だこれ?」と思って、それを外注に出したらSARSですって言われた。しかも同じ町で全く別々の2人の医師が同時に気付いた。
司会 これおかしいって思えたのもすごいですよね。実行に移したことも。
水本 普段研究していないお医者さんが、そこからウイルスのゲノム検査しようと思わないよね。
堀江 これは立派なことですよ。
水本 日本では検査をできても、ゲノム検査をするという発想に至らないと思う。
古瀬 全然、無理ですよね。
日本の感染症対策
司会 例えば、地方自治体とか県とか市町村レベルって、感染症を専門とする人って常駐してないんですか。
古瀬 常駐の人がいることはまずないですね。
司会 日本でも本当に医療が逼迫する可能性があるということですよね。
古瀬 保健所には何らかのプロが2~3人いて、そのなかに感染症の専門家がいたら本当にラッキーというくらい。
水本 職員数も減ってきている。今後起こり得る感染拡大に耐えられない可能性だってある。
司会 対策班メンバーが集まれるシステマティックな制度はないんでしょうか?
水本 自分が大学に研究室を持っていて、授業もあったら教員だって無理だよね。
司会 ちなみに対策班メンバーにはお金って出ているんですか。
古瀬 出るか、出ないか分からない状態で参加しましたが…最終的にはお金は出ました。参加した時点では、滞在費や交通費も、全部自腹になる可能性もあった。
司会 ボランティアですよね。
古瀬 2月に始まって、もう年度の予算が終わっていたので…。
水本 それだけだったらいいんですけど、本業の研究が止まってしまうのが痛いよね。社会貢献はしたいけれど、研究時間や研究費申請の逸失機会が多いので、継続の可能性があるかといわれると…。2度目の招集は全力でお断りしたい(笑)。
司会 研究者は声かけられても参加に悩むというか…断ってもいいわけですよね?
古瀬 経験を買いに来ているという感じになっていますね。
司会 クラスター班に入るんだったら、何とか業績に結びつけたいと集まる研究者も中にはいるんですか?
古瀬 それはないと思う。
水本 そこまではないですけどね。授業等や委員会とか全部止めて、詰めてやれるかって言うと、普通は難しいと思う。自分は、今回の場合は授業が止まったんで、ある意味行けたかもしれないですけど、状況によっては難しいですね。
司会 知人とかのネットワークで集まってきて、お金も出るか分からない、そんな善意の体制で感染症対策が支えられているって、大丈夫なのかなと。
水本 まったくその通りですよね。
司会 実務面の話で、こんなデータがリアルタイムに上がったらいいのになとは感じた点はありましたか?
古瀬 不足のデータというよりも、データの集め方が場所によってバラバラなんですよ。
水本 情報収集のフォーマットですね。今回、47都道府県が公表しているデータって、基本的にフォーマットも違うし、それを揃えるのに、膨大な時間と労力がかかっている。だから、全国統一のフォーマットなら効率も全く変わってくる。
古瀬 なかにはデータ送信がいまでもFAX?…なんて馬鹿にしましたけど、アメリカでも一部の州ではFAX送信ですね。
水本 都道府県によっては、事情があって、開示をしていないデータがあるので、そこも全部公開してもらいたいという希望はある。感染症は人権問題も絡んで開示していないデータもあるので、こういう緊急時にリスク推定が遅れたり、詳細な分析ができない要因にもなっているところがある。

政府権限による感染対策体制
司会 韓国とか台湾って、封じ込めに上手くいっている感じがありますが、日本とは何が違うんでしょう?
古瀬 医療体制とかデータの問題じゃなくて、政府権限の強さですよね。
水本 確か法律で、濃厚接触者のGPS追跡が可能で、韓国はGPSで外出監視が可能だったかと思います。さらに、まずマンパワーが違い過ぎる。
古瀬 韓国は、教会で人が1,000人ぐらい感染した。あれは、全部軍人を使って抑え込んだ。軍に所属する医療関係者たちが1週間、寝ずにやれみたいな感じで実施した。日本じゃできない。
水本 体制の違いで、できる可能性はあるけども、やれないんだよね。
司会 自衛隊にも感染症の専門家はいるんですよね?
古瀬 部署はありますよ。でも10人いるかいないかくらいですが。
水本 接触者追跡アプリをみんなが入れてくれたら、100%だったら全然感染状況も違ってくるよね。
古瀬 でもあのアプリ100%の人が入れても、Bluetoothをオンにしないと駄目で…。
水本 あれ、バッテリーの減りが早いから、多分みんなBluetoothをオンにしてないでしょうね。
司会 なるほど、色々と課題があるっていうことですね。政府権限の問題も絡んできて。
水本 感染は今後も1~2年か、あるいはそれ以上続くし、いろいろな面でトレーニングが必要になってくるでしょうね。
司会 効率よく人から人に感染が拡がっていく病原体に関しては、先進国の方が感染爆発しやすいというところがある。むしろ密度とかの問題がありそうですね。
コロナ時代の暮らしと変化
司会 コロナとの付き合い方でも、ステイホームを前向きに捉えようという社会的風潮も出てきましたね。
堀江 ハンコはなくしてほしいですね。
司会 フィジカルに必要があるものは何なのかというのを考えさせられたし、必要だと言っていたことが、根底から覆されている面はあるかもしれませんね。海外は、急速にオンライン化した。ツールの使い方が上手だなという印象です。
堀江 オンラインセミナーでおもしろいのは、海外の研究者の話を聞ける機会がぐっと増えた。でも、海外発信だと、日本時間の午前3時~とかもざらにある(笑)。
司会 日本最大の学会の一つ分子生物学会は、オンライン開催になりました。
堀江 最近、授業もそうで、オンライン科目が増えてくると、逆に講義の場所がなくなる。個室もないし、家とか、子どもがいるととてもじゃないけど仕事はできない…。
古瀬 テレワーク用の部屋みたいなのを借りないときついかなと。
司会 実際に、オンラインだけでも意外と社会は回るんじゃないか…ということにみんな気づいたんじゃないかって気がします。本日は、貴重なお話をありがとうございました!