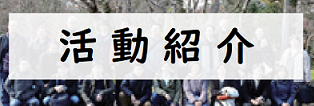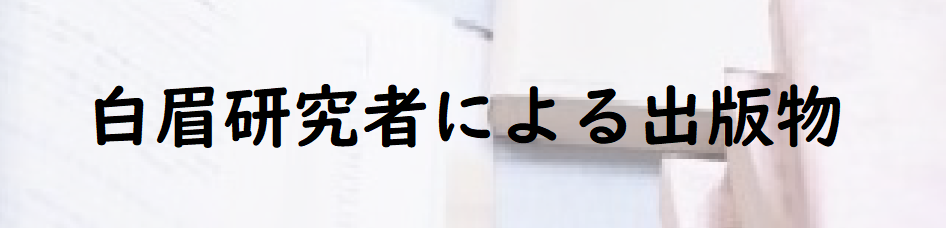刊行物
応募書類の受付は4月26日13時に締め切りました。
書類の受諾状況は、5月中旬頃に応募者登録サイトに表示されます。
"Application forms were closed at 13:00 on 26 April.
The acceptance status of documents will be displayed on the registration website around mid-May."
| ENGLISH |
坂本 龍太
深い山中の路上で、赤ちゃんの胸に聴診器をあてた。呼吸音も心音も聞こえず、瞳孔は散大していた。赤ちゃんの死亡を告げると、父親は泣き崩れた。赤ちゃんの祖父と親戚、診療所のスタッフと私は、穴を掘った。赤ちゃんの体を埋め、その上に石を重ねて、合掌した。意識から離れていることも多いが、週に何度か思い出す光景である。その度に自分の未熟さにため息が出る。そして、自分の元気な子供たちの顔を見て、なんと恵まれていることか、と感謝する。
「ドクター、急いで来てくれ!母親が死にそうだ!」切羽詰った声で呼ばれたのは8時間ほど山道を歩いて辿りついた村で、靴下を脱いで脚を伸ばしている時であった。高齢者健診に関する話し合いを行うための訪問だった。分娩後の母親の容体が悪く意識が朦朧としており、生まれた赤ちゃんもおかしい、という。私は産婦人科医でもなければ小児科医でもない。学生時代や研修医時代に何例か分娩を見学したが、知識も経験も欠落している。私はできることならその場から走って逃げ出したかった。でも私以外そこに医者はいない。急いで患者の所に向かうと、家の前で若い男性が一人心配そうに動き回っていた。不自由なのか片足を引きずっていた。彼が赤ちゃんの父親だった。中に入ると保健スタッフが青ざめた顔で叫んだ。「母親が死にそうなんだ!何とかしてくれ!赤ちゃんも変なんだ!こんなことは何年も助産をしていて初めてだ!」母親は血の気を失い青白くなっており、呼びかけに何とか薄目を開けて反応する状態だった。手首を触れると橈骨動脈が触れなかった。大腿動脈を触れると弱い拍動を感じた。子宮からの出血は落ち着いていた。見えにくくなっていた肘窩の静脈に針を刺し、かろうじて補液を開始することができた。幸い輸液に反応したのか脈拍や血圧は回復してきた。赤ちゃんを見ると、腹壁が大きく欠損し腸管の大部分が体外に脱出し、チアノーゼもあった。私も実際に目にするのは初めてであった。すぐさま小児科医と産婦人科医に連絡を取り、指示を仰いだ。これは腹壁破裂という病気で出生1万あたり1~5例と言われているが、日本であれば胎児の時にすでに超音波で診断がついていることが多い。亡くなることもあるが、近年では出生前から厳重な管理下に置かれ、手術により9割近くが生存できるはずだ。「すぐに病院まで搬送してほしい。清潔なガーゼに生理食塩水を浸し、清潔なビニールで包むように。チアノーゼがあるなら酸素を吸入させるように」私は小児科医と産婦人科医の指示に従い、ガーゼに生理食塩水を浸しビニールで覆った。しかし、日本のように袋に入った滅菌ガーゼなどはなく、普通のガーゼであった。診療所に酸素ボンベはあったが、中身は空だった。
日が暮れ始めてきていた。「直ちに母子ともに病院に搬送しよう」と言うと、保健スタッフは表情をこわばらせた。そこから車道に出るだけで6時間はかかる。雨も降り始めていた。「ドクター、そんなことをしたら運ぶ側が死んでしまうかもしれない」私は異なる経路でその村まで来たので、どんな道かを知らなかった。暗闇の中、雨でぬかるんだ細い山道を歩けば、足を滑らせて山から転落するかもしれないという。「何でこんな時に降らなきゃいけないんだ!」私は激しさを増す雨に対して無性に腹が立った。父親は我が子からはみ出る腸管を見て絶望し「病院へは行かない。母親の父も『この赤ちゃんはもう無理だ、このままここで死なせてほしい』と言っている」と話していた。「搬送途中で死ぬ可能性はあるが、無事に病院に着き手術をすれば助かる可能性がある。この村でただ死を待つよりも挑戦しよう。夜が危ないというなら朝4時にでも出発しよう」と言ったが、了解は得られなかった。その後も説得を試みたが父親は首を縦に振らなかった。母親の状態は落ち着いてきていたが、赤ちゃんの方はこうしている間にも死んでしまうかもしれないと思った。夜明けが近づいた頃、父親は寝ている赤ちゃんに近寄り、抱きかかえた。赤ちゃんの頬を指でさすり、笑みを浮かべた。しばし赤ちゃんを見つめていた父親は意を決したようにこう言った。「ドクター、この子を何とか救いたい。ダメかもしれないけど、父親としてこの子のためにベストを尽くしたい!病院に行こう!」外を見ると雨は小降りになっていた。朝日の柔らかい光が差し込み、私は心から感謝した。新生児用の補液機材は無く、産婦人科医と電話で相談の上、乳児がいる親戚の女性に授乳してもらっていた。リスクはあった。その女性や反対していた祖父も付き添ってくれることになった。父親は足を引きずりながら歩みを始めた。村の出口まで来た時、父親は立ち止まり、マニ車を回した。涙を拭いながら懸命に祈りを捧げていた。その姿を見て私は涙をこらえることが出来なかった。
5時間近く歩いた時、赤ちゃんは懸命に母乳を吸っていた。あと1時間で救急車が待機している車道に出る。何とか病院まで辿りつけるかもしれないと期待した矢先、赤ちゃんを抱いていた祖父が足を止めた。つい先ほどまでミルクを飲んでいた赤ちゃんが突如として息絶えてしまったのだ。木が鬱蒼と茂る中、赤ちゃんの亡骸を前に我々はしばらく呆然と立ち尽くした。そして、泣いた。なぜ赤ちゃんは死ななければならなかったのか。ヘリコプターは無理だと言われたが、保健省中枢にいる友人に相談すれば手配が可能だったかもしれない。立ち会った者が私ではなければ、赤ちゃんの命をきちんと助けることができたかもしれない。「赤ちゃんの命を守ることが出来ず、申し訳ございませんでした」私は父親に頭を下げた。父親は私の手を握りしめ、涙を流しながらこう話した。「俺たちは赤ちゃんのためにペストを尽くした。そうだろ、ドクター?」その時私は手を握りしめながら黙ってうなずいた。しかし、「できることが他にあったのではないか・・・」という想いが日本にいる今も波のように押し寄せる。何を言っても、あの赤ちゃんの命はもう戻っては来ない。
(さかもと りょうた)