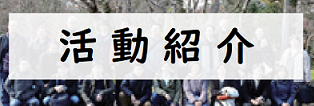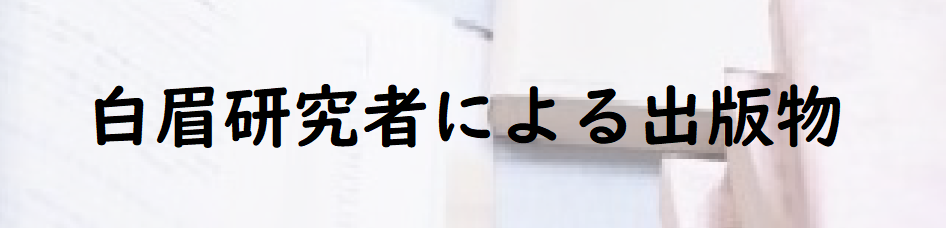刊行物
応募書類の受付は4月26日13時に締め切りました。
書類の受諾状況は、5月中旬頃に応募者登録サイトに表示されます。
"Application forms were closed at 13:00 on 26 April.
The acceptance status of documents will be displayed on the registration website around mid-May."
| ENGLISH |
鳥澤 勇介
生きた細胞を体外で培養する組織培養が提唱されて 100年以上が経ち、組織培養技術は様々な分野で欠かせない技術となっている。例えば創薬や毒性試験において、培養細胞を用いた評価手法はヒト体内での薬剤の効果をおおまかに予測でき、スクリーニングの手法として有効である。また、幹細胞研究や再生医療の実現に向けて体外での細胞培養は必要不可欠なプロセスである。しかしながら、このような細胞の培養方法は 100 年近く昔とほとんど変わっておらず、プラスチックのシャーレの上で細胞の培養を行う手法が未だに主流である。これでは細胞の置かれる環境が生体内とは大きく異なるため、生体内における細胞と体外での培養細胞とではその機能が異なっている場合が多く、ヒト体内の効果を予測する上で大きな問題となっている。そこで私は、工学の技術を細胞培養に応用することで、Organ-on-a-chip と呼ばれる新たな生体模倣デバイスの開発に取り組んでいる。これは、細胞の置かれる環境をできる限り生体内に近づけることで、臓器の機能の再現を目指す技術である。個々の細胞をシャーレ上で培養していては得られなかった臓器としての細胞機能が、細胞の集団として組織を再構築し、化学的・物理的な環境を模倣することで再現可能となっている。
細胞は周囲の環境と相互に作用することでその機能を維持しており、生体内の環境を再現することが細胞機能を維持する上で非常に重要となる。細胞のサイズがマイクロメートルオーダーであることから、細胞周囲の環境の再構築には、マイクロエンジニアリング技術が有効なツールとなる。特に、髪の毛の太さ程度の小さな管の中で細胞培養を行うマイクロ流体デバイスが、生体内の環境を再現する上で有効となる。デバイス上に作製した微小な流路内で細胞の培養を行うことで、生体内に類似した液量を再現でき、更に溶液の流れによる力学的な環境の再現が可能となる。一般的な培養手法であるシャーレによる培養では、大量の培養液で細胞培養を行うため、細胞に対する溶液量が格段に大きく、生体内の環境とは大きく異なっており、そのために細胞間の相互作用に起因する細胞機能を維持することが困難となっている。一方で、マイクロ流体デバイス内では、細胞に対する溶液量が生体内に類似して微小であるため、局所的な濃度勾配が形成可能であり、細胞間の相互作用が再現可能となる。例えば、血管の内皮細胞を微小な液量で培養を行うと、管状のネットワークが形成可能となる。これは、酸素濃度の勾配や分泌シグナルによる細胞間相互作用に起因しており、通常の培養手法では再現することは難しい。このようなデバイスを利用することで、最近では3次元のチューブ構造をした血管を作製可能となっている。作製した血管中には血液などの細胞を流すことが可能であり、体内の血管に類似した組織が作製可能となっている。血管は全ての臓器に欠かせない組織であり、栄養や血液細胞は、血管を介して各臓器に運ばれている。血管構造を再構築することで、比較的大きなサイズの細胞組織を体外で維持可能となり、更に血管を介した細胞間の相互作用が再現可能となるため、様々な臓器模倣デバイスの開発や癌などの病気のモデル化が可能となる。生体模倣デバイスは、ヒトの細胞を用いて臓器の機能を再現しているために、ヒト体内の挙動を予測可能である点に特徴がある。現在、創薬などで一般的に利用されている動物モデルでは、ヒトにおける臨床での結果と大きく異なる問題が指摘されており、このようなデバイスを用いた手法が動物実験の代替法となることが期待されている。近年、肺や心臓、腸や肝臓などの様々な臓器の模倣デバイスの開発が検討されており、これら個々の臓器デバイスを一枚のチップ上に配列することで、ヒト体内の挙動をモデル化する試みも検討されている。ヒト体内の挙動がチップ上で再現可能となれば、ヒト体内の薬の効果を精度よく予測可能となり、投与前に薬の効果を予測することも可能となる。将来、個々の技術の進歩により臓器模倣デバイスが動物実験の代替法となり、ヒト体内のモデルシステムとして利用されることが切望される。
マイクロ流体デバイス
デバイス内に作製した血管の中を血液細胞が流れている様子
(とりさわ ゆうすけ)