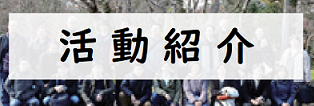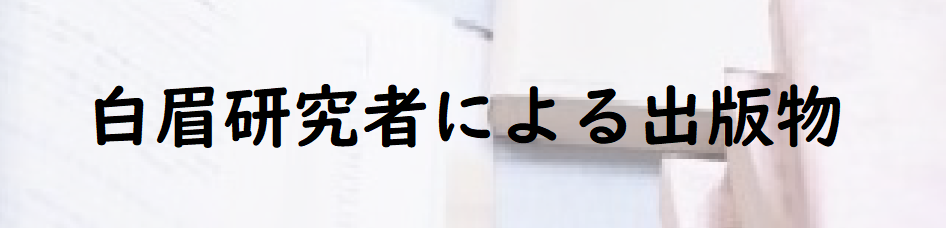刊行物
応募書類の受付は4月26日13時に締め切りました。
書類の受諾状況は、5月中旬頃に応募者登録サイトに表示されます。
"Application forms were closed at 13:00 on 26 April.
The acceptance status of documents will be displayed on the registration website around mid-May."
| ENGLISH |
門脇 浩明
生態学者(ecologist)というものは、地球上の生物(ヒトを含む)が存在するあらゆる環境を舞台として研究を展開している。これは生態学が扱う対象生物や研究手法が多様であり、生態学者自身も多様であることを意味している。よって、本稿では、私個人の研究内容を紹介するのではなく、生態学とは全体としてどのような学問であり、生態学者は何をモチベーションに研究をしているのかについて私見を述べてみたい。それらを通じて、私自身の研究にも興味を持ってもらえたら幸いである。
面白いと言われたい生態学者
生態学者が研究内容を賞賛する時に発する言葉は他の分野と少し異なるのではないか。そう感じたのは、研究室に配属された4回生の頃だった。セミナーで誰かが素晴らしい研究発表をした時、教授や院生らは口を揃えて「これ(この研究)は面白い」というのである。面白いというのは勿論「滑稽である」という意味ではなく、好奇心をそそるという意味で英語のinteresting に似ているが、生態学者が用いる「面白い」はinterestingよりもさらに深い意味を持つ。研究の着想から実験計画、得られた結果から導かれる議論に至るまで独創的で誰も考えつかなかったようなストーリー展開こそが面白い研究の証である。だから、「面白い」という言葉は生態学者にとって最高の褒め言葉となる。研究として意義があるのかどうかを重要な評価基準とする学問分野が多いなか、これほど「面白い」ことを評価の物差しとする分野は珍しいのかもしれない。他の多くの分野では、科学者としてやるべきことが明確に決まっていて、その目指すべき方向や答えに対し如何にしてたどり着くのかが問題であり、その過程に敢えて面白さを追い求める必然性はないのかもしれない。では、なぜ生態学者はこれほど面白さに執着するのだろうか。
生態学者とその他の分野との違いを考えるとき、いつも思い出すのは卒論研究を始めた頃にお世話になった異分野の先生から言われた強烈な一言である。「生態学者は数を数えるか、測るかしかやっとらんやないか。ほかの生物学者はどうやって測るかを真剣に考えとるというのに、お前らはそんなんで仕事になるんやから呑気なもんや。」と言われたのである。確かに、生態学の現場といえば、巻尺を持って山を歩き樹木の幹の太さを測ったり、網を持って魚をすくって個体数を数え上げたりする、そんなイメージを持つ人が多いだろう。この一言は、当時の生態学のアプローチのある一面を明確に言い当てているが、実は、生態学には色々な側面があり、さらにそれらの側面には時代とともに大きく変わった部分もあれば、変わらない部分もあるように思う。
変わったことと変わらないこと
生態学が時代とともに最も大きく変わった点といえば、DNAシーケンスなど分子生物学的手法や計算機性能の向上といった技術革新の波が押し寄せ、生態学にも新たな研究手法として積極的に取り入れられるようになったことだろう。遺伝子から生態系まで幅広い種類やスケールのデータを扱えるようになったことで、生物と環境の関わりをこれまで以上に包括的に、かつ大きなスケールにおいて解析することが可能となった。中には、環境DNA のような生態学分野の中から生まれた技術革新もあり、この分野におけるフィールド ワークのあり方を刷新してきた。
しかし、技術革新があっても尚、生態学には変わらない部分もあると思う。その最たるものが、「面白い」研究に対する生態学者の情熱である。冒頭に少し述べたが、生態学研究において高い評価が得られるかどうかは、面白いストーリーを組み立てることができるかにかかっている。ストーリーを組み立てるというと非科学的に聞こえるが、それは論理的な飛躍があっても良いというわけでは決してない。操作実験、理論生態学や数理統計モデリングなど、測定された生物現象の背後に潜むメカニズムを追求するからこそ発展してきた、生態学が得意とするアプローチによって浮かび上がるストーリーがある。野外・実験室・計算機などあらゆる場から得られたデータをもとに因果の連鎖を分析し、現象の背後にあるプロセスを一つ一つ組み立ててゆく。それらのアプローチによって、今日の生態学を形作る数多くの面白い研究成果が生み出されてきた。生活史戦略や最適採餌・ニッチ類似限界・キーストーン種などの古典的概念、植物土壌フィードバックや生態進化フィードバック・現代共存理論などの此処10―20年の間に発展してきた理論は、いずれも生物現象の背後にあるメカニズムを徹底的に考え抜くことで当時の生態学の常識を見事に塗り替えたストーリーの数々である。これらの原著論文を読むと、その面白いストーリーに辿り着くことができた著者らの興奮が蘇ってくるようである。こうして、時代とともに研究に用いる技術は変われども、生態学者が面白いストーリーを組み立てることに駆り立てられてきたという面は、昔も今も変わっていないと思う。
変わったことと変わらないこと
それでも、生態学者が面白いストーリーを追求したところで社会にとって何の意味があるのだろう、やはり呑気なのではないかと思われるかもしれない。たしかに、生態学は、医学のように直ぐに誰かの命を救えるわけでもなければ、工学のように研究成果が新しい技術となって産業に役立つわけでもない。社会への即戦力となりうる機会はそう多くはないかもしれない。しかし、生態学の研究が紡ぎ出す、地球生命のまだ見ぬストーリーは、これまでになかった切り口で世界の有り様を捉え、その捉え方を社会に直接的に還元することで、誰にとっても、そして、どんな社会にとっても長期的に役に立つ可能性を秘めている。なぜなら、生態学とは突き詰めれば、どうすればヒトと自然が持続的に共存できるのかを中心的な命題とする学問であり、今後ヒトがどう生きるべきなのかについて考えるヒントを与えてくれる学問でもあるからである。
生態学者は誰しも自分にしか描くことのできないストーリーを追い求め、日々自然現象と向き合い、導き出された答えは本当に正しいのかと自問自答しながら、浮かび上がるストーリーを描いては消し、描いては消しを繰り返す。その作業を通じて生まれた世界についての多様な捉え方は、生態学というレンズを通して、個人から地域社会、地球全体に至るまで様々なスケールでの問題構造を把握し、解決の糸口を見出すことに繋がるだろう。私がこれほどに生態学に魅せられ、情熱を捧げたいと思えるのは、面白い研究をすることで社会の役にも立てるかもしれないという生態学の可能性に賭けてみたいと思うからかもしれない。
本欄をお読みいただき、具体的な研究内容についてご興味をお持ちいただけた方は、白眉要覧の自己紹介のページ(https://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/pub/AtAGlance?pub_year=2021)、個人ホームページ(https://kohmeikadowaki.jimdosite.com)、拙著「遺伝子・多様性・循環の科学」(門脇浩明・立木佑弥編、京都大学学術出版)などを覗いていただければ幸いである。そこには未来へと残すべき生物多様性と持続的な共存への第一歩となる「面白い」があることを願い、今日も新たなストーリーを編み出していきたいと思っている。

写真:生態学者はデスクワークから、ラボワーク、フィールドワークまで面白い研究を実現するためなら、全部やるのである
(かどわき こうめい)