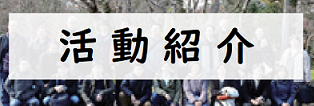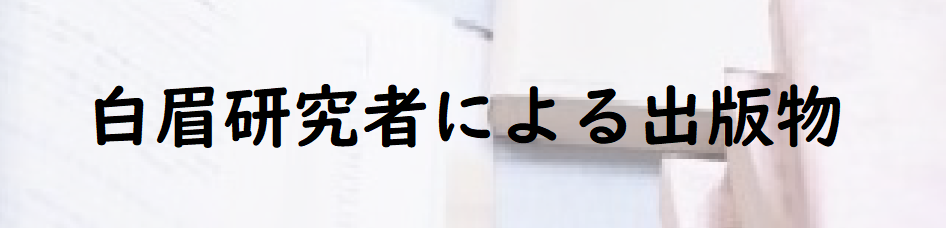刊行物
応募書類の受付は4月26日13時に締め切りました。
書類の受諾状況は、5月中旬頃に応募者登録サイトに表示されます。
"Application forms were closed at 13:00 on 26 April.
The acceptance status of documents will be displayed on the registration website around mid-May."
| ENGLISH |
西村 周浩
インドの古典語サンスクリット語がギリシア語やラテン語などヨーロッパ諸語とともに共通の祖先に遡るという仮説が 18 世紀末イギリス人文献学者 William Jones (1746-1794) によって提唱されて以来、様々な言語の音韻・形態・統語法の比較研究が行われ、その結果得られた構造的な対応関係から「印欧語族」が言語の一系統として確立、印欧比較言語学が研究領域としてその地歩を固めた。紀元前 4000 年頃に話されていたとされる印欧祖語の再建や特定語派内の言語史の構築といった作業はすでに 200 年という歳月に及んでおり、その伝統をドイツ、フランス、アメリカをはじめとする欧米諸国の研究者たちが支えてきた。彼らの関心は、自分たちの言語の源流に対する知的好奇心によって後押しされている。彼らが精神的基盤として育んできたヨーロッパ古典学の土台であるギリシア・ラテンの語学教育も、その好奇心を空疎なものにすることなく実りある知性へと高めていった。さらに、ゲルマン語やスラブ語など初期の文献が聖書の翻訳である場合、キリスト教徒としての日常的な関心が学問的なものへと昇華するといったこともあっただろう。
アメリカ人留学生でサンスクリット語研究者 アダム・キャット氏(左)と議論する筆者(右)
このような事情に照らすと、明治維新後西洋の学問を積極的に取り入れた日本は、その当時隆盛を極めていた印欧比較言語学に多くのことを学んだとは言え、研究の水準という点で欧米の「列強」に肩を並べられるほどの条件には恵まれていなかった。その不利な状況は今も厳然と存在していると認めざるを得ない。それでも、仏教の長い伝統を擁する日本は、サンスクリット語をはじめとするインド・イラン系言語に関して優れた人材を輩出してきた。立脚点は異なるが、日本が非印欧語系の国ながら印欧比較言語学への貢献の度合いを徐々に増してきたことは間違いない。さらなる発展の兆しもある。インド・イラン系言語の研究を足がかりに日本が国際的に広く人材を集める拠点へと脱皮し始めている点だ。この波は知的な刺激となって、日本におけるヨーロッパ系言語の研究にも好影響をもたらすかもしれない。今年 3 月にミラノで行われたラテン語関連の学会に日本から出席したのは私一人であったが、この孤立した状況は近い将来一変する可能性がある。
さらに、欧米諸国を有利にしていた「伝統」だけで研究を推し進めるのが難しいほどこれまでの成果が複雑に蓄積されてきたという点も、逆説的ではあるが日本にとっては好条件となっている。印欧比較言語学の領域において、データを眺めるだけであっさりと結論まで見通せるような研究テーマは限られてきている。かつては、すらすらとギリシア語やラテン語を読みこなすことで、音韻・形態・統語法についてざくざくと研究テーマを掘り当てるということがありえた。しかし、200 年以上の伝統は分野の地表面をしっかり整備された状態にしてくれたので、新たな鉱脈の発見はテキストの読解力に加えて言語学的手法のトレーニングに依るものが大きくなっている。技術を適正に磨くことで研究水準を向上させられるということは、日本にとって風向きのよい話だ。
伝統の蓄積:左はラテン語の代表的な語源辞典、右はテキストの注釈書
その一方で、分野全体にわたって音形や語形のある種唯物論的な分析が進み、テキストがもつ文脈を度外視する傾向が強まっている。印欧比較言語学は、古文献の扱いに関する経験値の高さが生んだ領域であると言っても過言ではない。テキストの膨大なコーパスを脳内に収めていたかつての研究者たちが根拠ある「直感」にしたがって次々と成果を生み出していった。今はそんな苦しい道を歩まなくとも、文法書や語源辞典、 電子化されたテキストでひとかどの研究ができるようになった。これは、日本人研究者にとってもありがたいことではあるが、分野全体の質や存在意義を揺るがすことにもなりかねない。言語活動は文脈を伴い、文脈同士の網の目の上に文献は成り立っている。そこに見られる音韻・形態・統語法などの言語現象は、その網を手繰ったり解いたりしながら進められるべきだろう。もちろん、その結び目のほとんどはすでに研究者たちの手垢まみれになっている。テキストが彼らとどんな付き合いをしたのか、その過去の全貌を目の当たりにすることは避けて通れない。それでもなお我々はテキストに対する一途な「想い」を持ち続けていく必要があるだろう。Quis enim modus adsit amori?(「一体どんな際限が愛にありえようか」― ウェルギリウス『牧歌』第 2 歌より)。
(にしむら かねひろ)