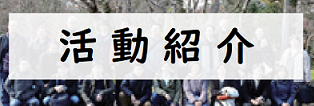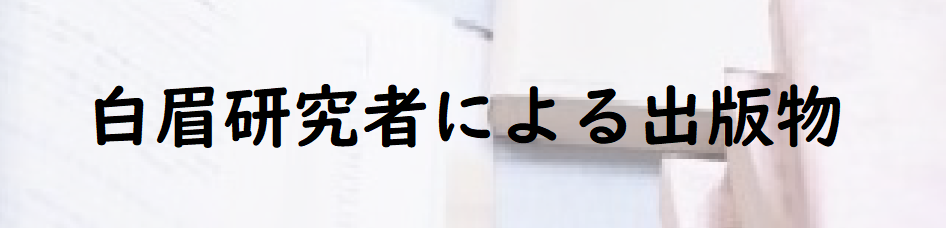刊行物
応募書類の受付は4月26日13時に締め切りました。
書類の受諾状況は、5月中旬頃に応募者登録サイトに表示されます。
"Application forms were closed at 13:00 on 26 April.
The acceptance status of documents will be displayed on the registration website around mid-May."
| ENGLISH |
細 将貴
月明かりに照らされて群青の海が広がっている。島を渡る湿った風がほおを撫で、背にした亜熱帯の山野へと吹き抜けていく。日暮れの前に降った雨は、今ごろ薄い霧となって森に立ち込めていることだろう。野帳に日付と時刻を記入し、車を降りながら懐中電灯を灯す。谷筋へと続く、簡易舗装のよく滑るこの道を1年ぶりに歩く。昨夏の台風になぎ倒されたと思しきハマイヌビワの大きな幹が、多数のひこばえを伴って道を塞いでいる。久しく木陰に甘んじていたクワズイモが、開けた夜空に向かってここぞとばかりに大きな葉を広げている。迂回して下草のなかを進むときには足運びに注意が必要だ。陰に潜むサキシマハブをうっかり踏んでしまえば調査どころではない。鉈を振るって道を拓いていく。苔で覆われ始めた、白いビニールテープが木の幹に見えた。センサスルートの始点である。
20 代から 30 代前半にかけての短からぬ時間を、私は独りこの西表島の森で過ごした。出会えれば奇跡と言って差支えのない稀産のヘビ、イワサキセダカヘビを捕えるためだ。このヘビは、珍しさだけでなく生き様の変わりぶりも屈指のもので、本種を含むセダカヘビ科の一族はカタツムリとナメクジしか食べないとされる。この幻のヘビを追うことは、ダーウィンの進化理論では説明できないとされていた、左巻きカタツムリの謎を解くためには必要なことだった。
カタツムリは、殻の巻き方向に応じて右巻き型と左巻き型に分けられる。どちらなのかは種ごとに定まっており、種内に両方の型がいる場合はほとんどない。逆巻きの相手とは交尾がしづらいからだ。仮に種内に両方の型がいたとしよう。数の少ない側の型は交尾相手に恵まれないため、自然選択を受けて徐々にさらに数を減らしていくと予想される。つまり最終的には元から多数派だった側の型に統一されてしまうのだ。ところがこの論理は、右巻きの種も左巻きの種もいるという現実にとって大変に都合が悪い。逆巻きの種が進化するためには、種内に突然変異で出現した逆巻き型がこの繁殖上の不利を乗り越え、子孫を増やすという過程を経る必要があるからだ。この進化過程には、何らかの未知のトリックが働いていたはずだ。
トリックスターは、きっとカタツムリを食べるヘビだ。私はそう信じた。最初の祖先が右巻きだったからだろう、カタツムリの世界では右巻きの種が圧倒的に多い。カタツムリの天敵からすれば、餌のほとんどは右巻きになるわけだ。そのため、天敵は右巻きを食べるのに特化する可能性がある。そのような「右利きの捕食者」がいれば、左巻きの種は多少なりとも進化しやすくなるはずだ。セダカヘビは実は右利きで、その分布する地域に限って左巻きカタツムリは頻繁に進化してきたのではないだろうか。
幸運と努力の甲斐あって、この「右利きのヘビ仮説」はいくつもの証拠から実証されたと言ってよいところにまで昇華することができた。その一方で、進化理論のほころびを繕う創造的な段階は完結したともいえる。そこで私は、この系を種分化研究のモデルたらしめることを目指すことにした。種分化とは、ひとつの種から新しく別の種が進化してくる現象、すなわち種の起源のことである。生命の進化において最も普遍的な現象のひとつであるとともに、ダーウィン以来綿々と解明が進められてきた究極の謎でもある。
この数年来、私は舞台を台湾に移し、新しい展望を求めて悪戦苦闘を続けている。面積では九州の半分ほどしかないとはいえ、最高峰が富士山を超えるこの島の自然は奥が深い。つい先日も新種と考えられるカタツムリを見つけてしまった。生物多様性の真の姿に近づくことができたのは間違いないが、道のりの遠さに目眩がしてしまう。いったい、どの種がどこまで分布しているのか。共存する種の組み合わせに発見したつもりのおぼろげな法則は、どこまで適用できるのか。そもそもこの法則の意味するところは何なのか。今はまだわからないことだらけで、成果が形になるまでにはさらに時間がかかりそうである。また今年からは、意を決して解読を始めたカタツムリ・ゲノムの茫々たる山野も拓いていかなくてはならない。月明かりを道しるべに、今夜も森にひとり。
新種と思われる左巻きのカタツムリ。
(ほそ まさき)