シリーズ白眉対談11「生物学の様々な視点」(2016)
生物研究の多様性
(司会) じゃあ古いってのは今とどう違うんですか。
(原村) 何ていったらいいんでしょうかね。何が古いというか、
(山道) エソロジー(ethology:動物行動学)と呼ぶか、ビヘイビアルエコロジー(behavioral ecology:行動生態学)と呼ぶか。
(原村) 僕がやってるのは、動物の行動を見て、その行動の意味や、どういった行動パターンなのかを見ていく感じなんですけどね。行動生態学のほうは、さらにもうちょっと適応進化とか適応度とかそういうのを入れて研究するっていう分野ですかね。
(山道) 4 つの問いを割と満遍なく扱うのが古典的動物行動学で、究極要因に特化するのが行動生態学みたいなイメージですかね。
(原村) そうですね。僕のイメージはそんなイメージですね。だから僕の興味の対象は結構広いんですよ。そういった意味では加賀谷さんおっしゃったみたいに、適応進化にも興味があるし、リリーサー3 や超正常刺激とかにも全部興味があるので。超正常刺激ってのは、知ってますよね。
(越川) 原村さんの授業受けてますからね。一緒に授業やってるんで。
(原村) 例えば、地面に巣を作る鳥などではたまに、自分の巣の中に産んだ卵が転がっていっちゃう。その卵をお母さんが、ちゃんと自分の巣のところにくちばしで戻す行動があるんです。でも、お母さんは自分の卵の大きさは、あまりちゃんと認識していなくて。例えば、わざと大きな卵を人工的に作ってあげてお母さんの近くに転がしてあげると、自分の卵よりも明らかに極端に大きい卵のほうを積極的に自分の巣に戻そうとするんですよね。そういったふうに普通ではあり得ない刺激のほうを好む、その刺激のことを超正常刺激って言うんです。
(加賀谷) それ言ったのティンバーゲン?
(原村) コンラート・ローレンツ4 とティンバーゲンですね。で、今、僕が外来種のオオヒキガエルでやろうとしてるのは、カエルって求愛するときに雄が鳴いて雌を呼びますよね。雌には鳴き声の好みがある。多くのカエルでは周波数が低い鳴き声のほうを雌は好むんです。なぜかっていったら体が大きいと鳴き声の周波数が低くなると。そうすると雌としては、できるだけ大きな個体と交尾したいから、低い周波数の鳴き声を好む。そういった鳴き声を人工的に作れないかなと、もっと雌にもてる鳴き声を作れないかなと思っています。
(加賀谷) 超正常刺激を作る、みたいな。
(原村) そうですね、今実験してるんですけど、オオヒキガエルでもやっぱり雌は人工的に低くした周波数の鳴き声のほうに集まってくるんですね。だからそれをうまいこと防除とかに使えないかなと。
(加賀谷) もう何か低すぎてカエルの声に聞こえないみたいになったりしないですか?
(原村) どこまで低くできるかはまだわからないですけどね。とりあえずパソコン使って実際に野外で周波数を加工した鳴き声を流すと、雌は低い周波数の鳴き声によってくる。雄の場合はコーラスっていってみんながたくさん鳴いている場所に集まるという報告があったんで、コーラスを人工的に作って流してあげると雄はそっちに反応するんですよね。なので、そういう昔発見された超正常刺激とかを、うまいこと利用して外来種の防除に使えないかなって、今研究していますね。僕としては結構面白いです(笑)。
(加賀谷) 僕は、ニューロ・エソロジーでちょっと動物行動学から派生した、むしろ視点としてはメカニズムのほうに特化していったようなところの研究をしてます。だからニューロンの活動とか、神経系のメカニズムの言葉で行動を説明しようとする。
(山道) ニューロ・エソロジーの祖というのは、ティンバーゲンですか。
(加賀谷) フランツ・フーバーとかご存じですか。コオロギ使ったニューロ・エソロジーの父と呼ばれています。あるいは、ウイルスマとか。ザリガニでニューロ・エソロジーの父になるのかな。職人芸でウイルスマがやった方法をまねることで僕は成果が出たんですけど、ザリガニの神経軸索の束を針で裂くっていうことをやりました。
(越川) それを裂いてどうするんですか。
(加賀谷) 裂くことではじめて、軸索束の内側にあって記録できなかったニューロンに電極を当てることができるようになったんです。ウイルスマたちはそれを裂いて電気刺激するっていう実験をいっぱいやって、その結果コマンドニューロンという考え方——もうある意味信じられてない部分があるんですけど——1 個のニューロンを刺激すると一つの行動が出てくる、という考え方を提唱したんです。
(越川) その神経の電位が取れるようになったっていうのはいつなんですか。エソロジーの確立よりも遅いわけですよね。
(加賀谷) そもそも動電気現象ってガルヴァーニが見つけてるんで5。
(越川) そんなに古いんですか。
(加賀谷)そう。ボルタとガルヴァーニのやり取りがあって、ガルヴァーニがカエルで見つけてるんですよ。ガルヴァーニはボルタにめちゃめちゃにやられるんですけど6。だから最初の動電気現象がそもそも、まず筋肉7。
(越川) 電気が神経から出ていて、筋肉を動かしているというふうなことがわかったのはいつですか?
(加賀谷) 18 世紀後半です。そして、さらにずっとその後20 世紀中盤に、神経インパルス、その電流が取れるみたいになった。イカの巨大軸索を使った電位固定実験です。細胞が巨大だから電極2 本入れることができる。電位固定することで電流を計ることができる。そして、僕が最初に神経インパルスに出会ったのが、大学4 年生のとき。研究室行ってオシロスコープだとか、電子機器がいっぱいあるようなところに行って、生物学の研究室っぽくないなっていうところで、とにかくやってみろと、(ガラス管微小電極を)挿してみろみたいな感じで、とにかく繰り返しよくわからないでやって、最初に静止電位がとりあえずとれるみたいな。次にスパイク活動が細胞外的に見えてきたものがきれいに挿さったら、きれいに活動電位波形が見えて、さらにシナプス加算が起きてるのが見えるとなってくると、おお、こんなんなってるんや、ほんまにっていう感動があって。
(越川) それはやっぱり挿し方、テクニックですよね。
(加賀谷) そうですね(笑)、それはテクニックですね。テクニック。オシロスコープ見ながら挿していく、ブラインドで挿していくんで、こうぽんぽんってタッピングしながら、機械的に。あるいはフィードバックの回路を発振させて入れるっていうことやりながら、オシロスコープ見ながら、叩いていく、あ、何か細胞近くに来てるなみたいな状態になって、こんっていって、すぱっとこうやって、しゅぱしゅぱ! と。
(一同) (笑)
(加賀谷) こう出てくると「おお」、みたいな(笑)。だんだんあれなんですよね、報酬になってきて、
(越川) 自分の行動も変わってしまった?
(加賀谷) そうそう。その報酬を求めにこう手を動かしてしまう。
(越川) (手の動きをまねて)これは何です? マニピュレーターなんですか。
(加賀谷) そうです。マニピュレーターで少しずつ動かすマニピュレーターなんですけど、それ全体を機械的に振動させて入れるんですけど、タッピングも人によっていろいろスタイルが違って、人指し指使う人、中指使う人、テーブルを叩く人みたいに違う。僕は直接マニピュレーター叩くスタイルでした。
(原村) テーブルでもいいんですか。
(加賀谷) テーブルでも結構振動はいきます。だから、挿さってる状態で、その状態で何か誰かが、がーっと加賀谷くんどうだとか言いながら実験室のドア開けて、ぱーんと抜けてしまって、はぁ、ということも。
(一同) (笑)
(加賀谷) いうこともあるんで、実は今、実験中、取り込み中みたいな感じで。
(越川) 人払いをするわけですね。
(加賀谷) うん、でも最近やってなくて、こういう実験。ザリガニでそういう感じでやってたのを、ちょっと違う視点でっていうことで、違う生き物を考え出したんですね。ところで、生き物変えるタイミングって結構その、
(山道) 難しいですよね。
(加賀谷) 博士取った、あるいはポスドク終わるタイミングがあると思います。僕の場合、ザリガニ以外の面白い何かっていう感じで探しました。もともと自発的に行動する動物の行動のメカニズムに興味があったんで、環境で逐次フィードバックを受けていて制御に使っているとかっていうことじゃなくて、フィードバックがなくても明らかに行動を制御してるようなっていうのを頭のどこかで探していて、シャコパンチに出会った。シャコのパンチは2 ミリセカンドぐらいですから、運動始めちゃったら変えることなんてできないんですよね。崖飛び降りるみたいなことになるんですよね。で、じゃあどうやって制御してんのという疑問になりました。それでシャコを研究者でやってる人いないかなと思って検索すると、バイオメカニクスの人がアメリカにいて、そうかと思ってコンタクトとりました。
(原村) シャコ研究者っていっぱいいるんですか。
(加賀谷) 視覚研究者は比較的いますね。生理学。あと行動生態学で。
(越川) どのくらい。世界に100 人?
(加賀谷) そのぐらい、いやそんなにいないかも。そういう意味で人口が少ないので普遍性っていうの難しいですよね。みんなが共通の問題に対して取り組んでたり、あるいは何かもう既に問題の切り分けができていて、この問題はあそこでやってる、この問題は別のところでやってるみたいな。
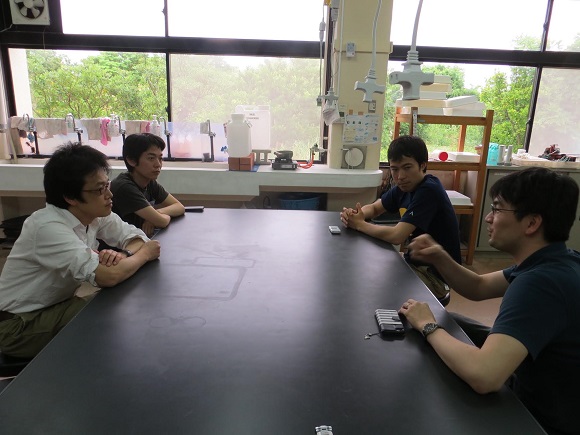
研究対象の生き物

(司会) 一つ聞きたいのですが、さっき対象として生き物を変えるときのタイミングは難しいんだっというところで、皆さんがうなずいていらっしゃったのですが、山道さんは対象の生き物っていうのは変わっているんですか。
(越川) 山道くんは何か変え放題だから。
(一同) (笑)
(山道) 卒論はシカで、大学院の研究はプランクトンとヒトとチンパンジーとカタツムリとヘビとグッピーの研究をしていて、最近は水草とプランクトンと、あとカッコウとキタゾウアザラシもちょっと。
(加賀谷) めっちゃ変えてるじゃないですか。
(一同) (笑)
(司会) それでも対象を変えるのは難しいんですか(笑)。
(越川) 数理だから変え放題ですよね。
(山道) いや逆に、数理ってどういうふうにキャリアを組み立てていくのかが難しいなって最近思っていて。何か一つに決めてやると、自分の中の軸が決まるじゃないですか。逆にいろいろやっちゃうと、周りから「何をやっているのかよくわからない人」っていうふうに見られがちだし、やっぱり特色が出ないとなかなか認知を獲得しづらいんじゃないですか。
(越川) じゃあ、1 個に決めましょう。
(山道) 一応プランクトンがメインなんですよ。プランクトンメインで、カタツムリ副ぐらいで。
(司会) 生物学者はやっぱり対象となる生き物にこだわって、その生き物のものをしっかりと調べることで、生物学の何か統一的なものを知りたいっていうところがあるのでしょうか?(様子を伺いながら)・・・・そういう感じでもなさそうですね。
(一同) (笑)
(司会) 単にその生き物が面白いから研究しているという部分もあるのでしょうか。
(加賀谷) いや、面白いだけ、どうかな。
(原村) 僕は卵が好きなんですよね。
(一同)( 笑)
(原村) 僕も卒論のときは研究室も全然違って生態学の研究室で、野良ネコを調査していました。今は趣味で飼ってるんですけどね。野良ネコの調査をやってて、今「卵」に関心があるっていう理由の一つが、母性効果っていってお母さんの効果が子どもにどう影響するかっていう研究分野があって。哺乳類とか、お母さんが子育てする生き物では、やっぱりお母さんの行動がそのまま、そのままっていうかある程度子どもに影響するんですね。それでふって思ったのが、じゃあ生まれたときにお母さんがいない生き物はどうなんやろうって、それで卵がすごい気になり始めて。それでカエルを研究し始めたんですね、卵を産むんやったらカエルやろっていう(笑)。最初はだからお母さんの産卵場所選択とか、そういう研究をしてました。で、今はオオヒキガエルの防除研究やってるんですけど。オオヒキガエルの研究目標は防除なんだけれども、やってることはやっぱり卵に関係することなんですよね、卵の共食い行動を利用した防除みたいな。今、僕は一応カエルをやってる研究者なんですけど、何やってる研究者って言われて一番うれしいのは、卵やってる研究者って言われるのが一番うれしいんですよね、僕的には。
(越川) 今まで、完全にカエルの人って思っていました。
(一同) (笑)
(越川) もっと卵を押してったほうがいい。
(加賀谷) 卵の人(笑)。
(原村) 卵っていったら動物の生活史の中の最初の少しの部分でしかないので、そこだけに注目してる人ってほとんどいない。
(越川) 卵の原村でいったらいいじゃないですか。